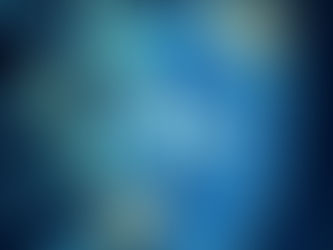保護者が身につけておくべき情報セキュリティの基礎知識
- Pipeline Co. Ltd.
- 2022年12月15日
- 読了時間: 6分

お子様への家庭での情報セキュリティ教育が重要性を増しています!
経済のグローバル化が進むとともに、世界中にインターネット網が構築されたことから、情報のグローバル化も進みました。さらに、そうした情報を利用したビジネスがグローバルに展開されてきました。そして、それらのニーズに対応すべく、情報システムのクラウド化が進みました。
クラウド化により、情報やシステムが実際に置かれる所在地がグローバル化され、情報システムの利用国と、システム上の情報の所在国が必ずしも一致しなくなりました。しかし、国の法律は基本的にその国の範囲内にしか及ばないので、自分の国の法律によって守られるべき情報がどこにどのように置かれるのかをしっかり意識する必要が出てくるようになりました。
このことは、今年2021年3月になって、コミュニケーションアプリ「LINE」の情報管理に関して懸念が報道1)されるようになってから多くの人に認識されるようになりました。
「LINE」は日本においてユーザ数8600万、つまり日本国民の7割が利用しており、メッセージ交換にとどまらず、LINE PAY、LINE NEWS、LINE WORKSなど、生活やビジネスに活用される様々な機能を統合したサービスであることから、多くの企業や行政サービス(例えば、新型コロナ対応におけるアンケートやワクチン接種情報の提供)でも利用されており、日本の情報インフラの一つになっています。
もちろん、情報サービス事業者は通信内容やシステム上の情報を暗号化することにより、単純に第三者が通信内容を傍受したり、システム上の情報を取り出したりしても、簡単には情報漏えいの実害が無いように対策はしています。しかし、今回問題になったことは、日本企業を含め、中国においてビジネスを展開する外国企業が度々目の当たりにする、中国における情報通信の法規制(暗号データ規制や中国政府への情報提供など)の解釈と適用が中国政府の思惑によって変わってくるのではという懸念です。
「LINE」に関する今回の報道は、何年も前から存在していた中国政府の法規制に対する懸念の背景があったところに火がついたといえるかもしれません。
さて、私たちの普段の生活に視点を移してみると、ほとんどの人がスマートフォンやタブレットなどを常に持ち歩いており、起きていても寝ていても、操作をしてもしなくても、常にそれら端末はインターネットに接続して情報を交換しています。
このような中、普段の生活における個人情報含め様々な自分の情報がどのように流れているのかはITに詳しい人でさえも完全には分からないし、それ以外の人でも、それを知らなくても問題なく生活していける、という生活様式になりました。
一方、情報セキュリティに関する問題は身近なものとなったことから、お子様を持つ保護者は今回のような報道を見聞きすると、自分が気をつけるのはもちろんですが、お子様が情報セキュリティに関する被害を受けないか不安にもなります。
お子様にスマートフォンを使わせていれば、正しく使っているのかとか、ゲーム端末もインターネットに接続するので、そこから問題が起きないかとか、心配の種は尽きません。
しかし、心配しているだけでは問題は解決しません。まずは問題が起きる状況を整理して、気をつけるべきポイントは何なのかを明らかにするところからスタートしましょう。これは今後、解決に必要な詳細な情報にアクセスための道筋を作ることにもつながります。
どのような場面でインタネットセキュリティの問題が発生するのか?
まず、インターネット利用に関して、どのような場面で、どのような問題が発生するのかを見ていきましょう。
インターネット利用における情報アクセスの場面は、以下のように大きく3つに分けられます。
情報取得・・・Webブラウザで検索またはURL入力でアクセスなど
情報発信・・・動画配信サイトに自分が撮影した動画をアップロードして公開する、SNSに記事を投稿するなど
情報交流・・・SNSや動画配信サービス、ブログなどのコメント欄での応答、ZOOMやLINEビデオ通話のようなミーティングサービスなど
このような①〜③のポイントにおいて発生する可能性がある問題を考えてみます。
①情報取得ですが、
特にWebブラウザ上で発生するのは、検索した結果のアクセス先やバナー広告のクリック先に詐欺や詐欺まがいの情報が掲載されている場合です。
このような情報を掲載する者は、なるべく多くの人がサイトを訪問する機会を作ろうとするため、ついついクリックしたくなるような言葉が見えるように、タイトルや画面を工夫しています。
このため、このようなサイトのアクセス数は多くなる傾向があり、検索サイトにおいて上位に入ってしまう可能性があります。
さらに厄介なことに、このようなサイトでは、アクセスした端末の情報を不正に取得される、不当に金銭を要求されるといったことも起きる可能性があります。検索サイトで上位にあるから安全とは限らないのです。
特にお子様が閲覧しやすい内容としては、ゲーム製品の機能を改変してゲーム進行を不正に有利にする情報や関連製品の情報、海賊版マンガサイトといった違法な状態でデータをダウンロードできるサイトの情報が考えられます。
検索サイトでのサイト検索、動画配信サービス上での動画検索などをする場合、なるべく有害な情報のために時間を費やすことを避けるためには、いくつかの情報源を確認する、偏った考えを持たず、中立に多面的に物事をとらえる、という姿勢が必要となります。
これについては、いくつか存在する事例をもとにした解説を次回以降でしていきます。
次に、②情報発信ですが、
会社などの組織に所属したことのある方であれば、会社などの情報セキュリティ教育で、機密情報の漏えいがSNSなどから悪気なく情報発信することによって発生する事例について教えられるでしょう。また、不当な差別、いじめ、発信する情報を見る人を挑発するような内容は、人に迷惑をかけるだけでなく、状況によっては犯罪にもなる可能性があります。
情報発信の中でも、撮影した動画や写真を使って配信することは、現在多くの人が行っており、自身や家族、身近な人のプライバシーにも配慮するよう注意する機会は増えています。インスタグラムやツイッター、Youtubeなど利用しているお子様は多いと思います。全てを禁止すれば、その場での危険性は下がりますが、そのままお子様が成長してしまうと、情報リテラシーの低い大人になる恐れがあります。保護者はお子様と一緒になって情報発信の正しい方法について学び合う姿勢が望まれます。
そして、③情報交流ですが、
これはインターネットを使った情報サービス利用で最も効果を発揮するものですし、新型コロナで現実になった世界的なウイルスパンデミックに対する新しい生活様式を模索する中、ますます将来性を期待される一方、お子様が犯罪の被害に遭う多くの事例の原因にもなっていることから、保護者は心配されることでしょう。
インターネット上の交流は情報の発信と取得を双方向に行うものなので、上の①、②をともに考えることになります。お子様に対して、道端で不審な人に声を掛けられても気軽に応じない、ということはよく言い聞かせることでしょうが、インターネット上でも同じことはいえます。インターネット上における危険を回避する方法について、次回以降考えていきたいと思います。
参考
1)LINE株式会社「ユーザーの個人情報に関する一部報道について」