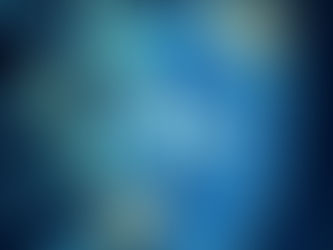アクティブサイバーディフェンスとは
- Pipeline Co. Ltd.
- 2022年9月1日
- 読了時間: 7分

アクティブサイバーディフェンス(Active Cyber Defense, ACD)は、サイバー攻撃に対する能動的な防御手法であり、攻撃を未然に防ぐための積極的なセキュリティ対策を指します。従来の受動的な防御とは異なり、ACDは攻撃の予兆を早期に検知し、攻撃元の特定や無力化を試みることで、被害を最小限に抑えることを目的としています。
1.ACD導入の成功事例
アクティブサイバーディフェンス(ACD)は、サイバー攻撃に対する能動的な防御戦略として、世界各国で注目を集めています。特に米国と英国が先駆的な役割を果たしており、その取り組みは他国のモデルケースとなっています。
米国は、ACDの実施において最も積極的な姿勢を示しています。2021年には、中国のHafniumグループによるMicrosoft Exchangeサーバーへの攻撃に対して、FBIが裁判所の許可を得て感染サーバーからWebシェルを削除する作戦を実施しました。
これは、政府機関が民間企業のシステムに直接介入してサイバー攻撃の被害を軽減した画期的な事例となりました。 さらに、米国は2023年1月にHiveランサムウェアグループのインフラを無力化する作戦を展開し、同年5月にはSnakeマルウェアの除去作戦(Operation MEDUSA)を実施しました。
これらの作戦は、サイバー犯罪組織の活動を直接的に阻害することを目的としており、ACDの攻撃的な側面を示しています。 また、米国は「Hunt Forward」作戦として、同盟国のネットワークに入り込んで脅威を探索・排除する活動を行っています。これまでに23カ国以上で50回以上実施されており、国際的な協力体制の構築と技術共有の重要性を示しています。 一方、英国は2016年からACDプログラムを本格的に開始しました。
国家サイバーセキュリティセンター(NCSC)が中心となり、2017年に公共部門向けのACDプログラムを立ち上げ、2019年からは民間部門への拡大を進めています。NCSCは毎年ACDの効果と新たな取り組みについて報告書を公表しており、透明性の確保と継続的な改善に努めています。 オーストラリアも2022年11月に、連邦警察とオーストラリア信号局(Australian Signals Directorate、ASD)が共同でサイバー犯罪シンジケートを調査・標的にし、破壊する常設作戦を開始すると発表しました。
この取り組みは、法執行機関と情報機関の連携によるACDの新たなモデルとして注目されています。 ルーマニアでは、2023年6月にルーマニア情報局のサイバー部門長が、外国のAPT(高度持続的脅威)グループの指揮統制サーバーをハッキングして無力化する計画を明らかにしました。これは、小国でも積極的なACDを実施する動きが広がっていることを示しています。
2.日本でのACD導入の課題
日本における能動的サイバー防御(Active Cyber Defense, ACD)の法整備には、いくつかの重要な要点を考慮する必要があります。
まず、憲法との整合性が大きな課題となります。日本国憲法は「通信の秘密」を保障しており、これを侵害しない形でACDを実施するためには、個人のプライバシーと国家安全保障のバランスを慎重に取る必要があります。ACDの活動を「公共の福祉」のために必要な合理的制限として位置づけることで、法的な整合性を図ることが求められます。
次に、情報収集と分析の範囲についても明確化が必要です。民間や重要インフラ事業者からの通信情報の収集・分析を可能にする一方で、個人間のメール内容など過度に私的な通信内容の収集は制限すべきです。
このような情報収集には独立監視機関の設置が不可欠であり、行政の対応を監視することで権力の乱用を防ぐ仕組みを構築することが重要です。
さらに、重要インフラ事業者にはサイバー攻撃を受けた場合、政府への報告を義務化する規定が必要です。ただし、この義務化には企業のレピュテーションリスク(評判や信用の低下のリスク)にも配慮する必要があります。
また、攻撃元への対応としては、必要に応じて攻撃元のサーバーに侵入し無害化する措置を講じる際の法的根拠を明確にし、自衛隊や警察などの能力活用を可能にする規定も求められます。
民間との連携も重要です。政府が入手した脅威情報を民間と共有し、対策を促す仕組みを構築する必要があります。同時に、機密保持の観点からの規定も必要です。中小企業支援としては、中小企業のサイバーセキュリティ対策支援に関する規定を設け、政府による支援を可能にすべきです。
人材育成もまた重要な要素であり、サイバーセキュリティ人材の育成に関する規定を設けることで、大学でのセキュリティ学科新設や社会人講座の促進を図るべきです。
国際協調についても、国際的な協力体制の構築や情報共有に関する規定を設け、グローバルなサイバー脅威に対応できるようにすべきです。
最後に、技術革新への対応としてAI等の新技術の活用や進化するサイバー脅威に柔軟に対応できる法的枠組みを構築する必要があります。
これらの要点を踏まえ、国民の理解を得ながら慎重かつ迅速に法整備を進めていくことが重要です。また、法整備後も定期的な見直しと更新を行い、急速に変化するサイバー空間の現状に対応していく必要があります。このような取り組みは、日本がサイバー空間で安全保障能力を向上させるために不可欠であり、今後も注力していくべき課題です。
3.ACDの実施には法的枠組みの整備や国際協調が不可欠
アクティブサイバーディフェンス(ACD)の実施には、法的枠組みの整備と国際協調が不可欠です。この重要性は、サイバー空間の特性と、ACDが持つ潜在的な影響力から生じています。
まず、法的枠組みの整備について考えてみましょう。ACDは従来の受動的なサイバーセキュリティ対策を超えた、より積極的で能動的な防御戦略です。これには、攻撃の予兆を検知し、攻撃元の特定や無力化を試みるなど、従来の法体系では想定されていなかった行為が含まれます。例えば、攻撃元のサーバーに侵入して無害化する行為は、現行法では違法とされる可能性があります。
そのため、ACDを合法的に実施するためには、新たな法的枠組みが必要となります。 この法的枠組みには、ACDの実施主体、許容される行為の範囲、監督機関の設置など、多岐にわたる要素を含める必要があります。
特に重要なのは、個人のプライバシーや通信の秘密といった基本的人権との整合性を図ることです。例えば、日本では憲法で通信の秘密が保障されているため、ACDの実施にあたってはこれとの調和が求められます。
また、ACDの実施には高度な技術と専門知識が必要となるため、人材育成や技術開発に関する規定も法的枠組みに含める必要があります。さらに、ACDの実施によって意図せず他国のシステムに影響を与える可能性もあるため、国際法との整合性も考慮しなければなりません。
次に、国際協調の重要性について考えてみましょう。サイバー空間は国境を越えて広がっており、サイバー攻撃も多くの場合、国境を越えて行われます。そのため、ACDを効果的に実施するためには、国際的な協力体制が不可欠です。 例えば、ある国がACDを実施する過程で、攻撃元が別の国にあることが判明した場合、その国の協力なしには対処が困難です。また、ACDの実施が意図せず他国のシステムに影響を与える可能性もあるため、事前の情報共有や協議が重要となります。
さらに、サイバー空間における行動規範や国際法の解釈についても、国際的な合意形成が必要です。例えば、どのような場合にACDの実施が正当化されるのか、ACDの実施によって生じた損害の責任はどのように分担されるのかなど、複雑な問題が存在します。
また、サイバー攻撃の手法や対策技術は日々進化しているため、各国が持つ知見や技術を共有することで、より効果的なACDの実施が可能となります。例えば、米国の「Hunt Forward」作戦のように、同盟国のネットワークに入り込んで脅威を探索・排除する活動は、国際協力の一例と言えるでしょう。
このように、ACDの実施には法的枠組みの整備と国際協調が不可欠です。これらは互いに密接に関連しており、一方だけでは十分な効果を発揮できません。法的枠組みがあっても国際協調がなければ、国境を越えたサイバー攻撃に対処できません。逆に、国際協調があっても各国の法的枠組みが整っていなければ、実効性のある対策を取ることができません。 したがって、ACDを効果的に実施するためには、各国が自国の法的枠組みを整備すると同時に、国際的な協調体制を構築していく必要があります。これは容易な課題ではありませんが、サイバー空間の安全を確保し、デジタル社会の健全な発展を支えるために不可欠な取り組みと言えるでしょう。