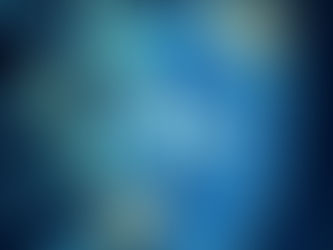CISOの役割変革:単なる「肩書き」から企業価値創造の中核を担う戦略的経営機能へ
- Pipeline Co. Ltd.
- 2023年11月1日
- 読了時間: 18分

1.はじめに:デジタル時代における情報セキュリティの戦略的意義
現代社会において、企業を取り巻くデジタルリスクは、その複雑さと巧妙さを増し続けています。サイバー攻撃は、単なる情報漏洩に留まらず、事業継続の脅威、ブランド価値の毀損、さらには社会インフラへの影響といった深刻な事態を招く可能性があります。このような環境下で、情報セキュリティはもはやIT部門の技術的な課題としてのみ捉えるべきものではなく、企業経営の根幹をなす戦略的な要件として位置づけられるべきです。
ここでは、最高情報セキュリティ責任者(CISO)の役割が、従来の技術的・リスク管理の範疇を超え、企業価値を創造し保護する重要な経営機能へと進化している例として、三菱電機グループとJALグループの具体的な取り組み事例を紹介します。CISOの役割を単なる「肩書き」から「責任構造の中核」へと昇華させることが、現代のデジタルリスクを乗り越え、未来を切り拓くための不可欠な投資であり、経営戦略そのものであることを、深く掘り下げます。
2.CISOの戦略的地位確立:組織責任構造の中核としての位置づけ
情報セキュリティを経営の最重要課題と位置づけ、トップマネジメントが直接コミットメントを示すことは、全社的なセキュリティ体制構築の出発点となります。CISOが経営会議に参画し、全社的な情報セキュリティ戦略を統括する権限と責任を持つことは、セキュリティに関する意思決定の迅速化と、必要なリソースの適切な配分を可能にする上で極めて重要であると認識されています。
三菱電機グループは、情報セキュリティを「企業経営の根幹をなす重要な経営課題」と深く認識し、その強化に継続的に取り組んでいます。この揺るぎない姿勢は、単なる法令遵守にとどまらず、企業全体のレジリエンスと競争力を向上させるための戦略的な投資であるという経営層の共通理解があることを示しています。この認識があるからこそ、情報セキュリティに関する予算配分、人材配置、組織体制の構築において、部門横断的な優先順位付けと必要なリソースの確保が円滑に進められています。
三菱電機グループの情報セキュリティ管理活動全般を統括するのは、三菱電機株式会社の常務執行役です。この「常務執行役」という役職は、CIOが経営会議のメンバーとして、全社的な経営戦略と情報セキュリティ戦略を密接に連携させる権限と責任を有していることを意味します。
これにより、情報セキュリティに関する意思決定が迅速かつ効果的に行われ、必要なリソースが適切に配分される仕組みが担保されているのです。これは、情報セキュリティが経営の意思決定プロセスに深く組み込まれていることを示しており、セキュリティリスクが事業リスクとして適切に評価され、経営層がその軽減策に直接コミットする「セキュリティ・バイ・デザイン」の経営アプローチが推進されていると解釈できます。
さらに、2020年4月には社長直轄組織として情報セキュリティ統括室が設置され、情報セキュリティ管理活動全般を統括する中核を担っています。この「社長直轄」という体制は、情報セキュリティが特定の部門の責任ではなく、経営トップが直接監督する全社的な課題であるというメッセージを明確に発しています。
一方、JALグループもまた、情報セキュリティの強化を「経営における最重要課題の一つ」として明確に位置づけています。これは、航空事業が社会インフラとしての重要な役割を担い、顧客の個人情報や運航に関する機密情報など、極めて重要な情報資産を多数取り扱う特性を持つため、情報セキュリティへの脅威が事業継続性や社会的信頼に直結するリスクとして認識されているためです。
JALグループ全体の情報セキュリティリスク管理・推進の最高責任者は、代表取締役社長が務めており、これにより、情報セキュリティが経営の根幹をなす重要事項として、トップダウンで推進される体制が確立されています。CISO(Chief Information Security Officer)は、デジタルテクノロジー本部を管掌する取締役副社長執行役員が務め、情報セキュリティを担う専門組織を配下に設置し、その組織を指揮監督しています。CISOの主要な役割は、ISO2700(情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格)や、国土交通省が定める「航空分野における情報セキュリティ確保に係る安全ガイドライン」に則り、情報セキュリティ強化に必要な対策を推進することであり、これはCISOが単なる技術責任者ではなく、経営戦略に直接関与し、組織全体に影響力を持つ存在であることを示しています。
情報セキュリティに関する意思決定とリスク管理のための会議体も整備されており、「グループリスクマネジメント会議」の下部会議体として「情報セキュリティ・個人情報保護委員会」が設置され、専門的な議論と意思決定を担っています。
これらの事例から、情報セキュリティの「経営課題化」と「トップダウン推進」は、現代企業にとって必然的な流れであることが明確になります。経営トップが情報セキュリティの最高責任者を務める、あるいはCISOが経営層の一員であることは、単なる形式的なものではありません。
このトップダウンのコミットメントが、情報セキュリティに関する予算配分、人材配置、組織体制の構築において、部門横断的な優先順位付けと必要なリソースの確保を円滑に進めるための強力な推進力となるのです。経営層が直接関与することで、情報セキュリティに関する意思決定が迅速かつ効果的に行われ、セキュリティリスクが事業リスクとして適切に評価されるようになります。これは、企業が直面するサイバー脅威の高度化・巧妙化に対応するために不可欠な意思決定のスピードと質を担保します。
さらに、三菱電機の事例に見られるように、情報セキュリティが事業戦略の策定、M&Aの検討、新規事業の開発といったあらゆる経営判断において考慮されるべき要素となり、結果として企業の持続的な成長に不可欠な競争優位性をもたらす可能性を秘めていると解釈できます。
JALの事例では、航空事業という社会インフラとしての特性上、情報セキュリティが事業継続性と社会的信頼に直結するリスクと認識されており、トップマネジメントの関与がこれらの基盤を揺るぎないものにしていると読み取れます。CISOの戦略的地位確立は、単に「リスクを管理する」という守りの機能を超え、「企業価値を創造し、保護する」攻めの経営機能へと進化させるための、組織的な基盤そのものなのです。これは、現代の企業がデジタルリスクを乗り越え、未来を切り拓くための不可欠な投資であり、経営戦略そのものであるという、本報告書の核心を裏付けています。
3.迅速なインシデント対応と継続的改善を可能にする明確な役割分担と体制
情報セキュリティインシデント発生時の被害を最小化し、迅速な回復を可能にするためには、多層的かつ明確な役割分担を持つ組織体制が不可欠です。これには、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)やPSIRT(Product Security Incident Response Team)、OTセキュリティ担当グループといった専門組織の機能と、それらが連携する仕組みが重要になります。また、PDCAサイクルに基づく継続的な改善活動、定期的な訓練、内部・外部監査、そして外部組織との連携は、変化する脅威に対応し、組織のレジリエンスを高める上で欠かせない要素です。
三菱電機グループの情報セキュリティ体制は、CIOを頂点としつつ、2020年4月に社長直轄組織として設置された情報セキュリティ統括室を中核に、各事業部門や専門分野に特化したチームが連携する多層的な構造を特徴としています。
情報セキュリティ統括室は、「企業機密管理・個人情報保護」「情報システムセキュリティ」「製品セキュリティ」の三機能を統合し、継続的に体制と陣容を強化・拡充しています。この統合は、情報セキュリティが技術的側面だけでなく、法務、コンプライアンス、製品ライフサイクル全体にわたる広範な領域をカバーしているという認識に基づいています。情報セキュリティ統括室は、各情報やシステムを利活用・管理する各事業本部や事業所に設置されたCSIRTと相互に連携し、情報セキュリティの確保に努めています。
さらに、工場の生産に影響を与えるサイバー攻撃に対応するため、OTセキュリティを担当する専門グループも設置し、体制を強化しています。このOTセキュリティ専門グループは、Purdue参照モデルをベースに、工場内のシステムや機器の設置位置を論理的に層別し、各層に対するセキュリティ要件を明確化・文書化して対策を推進しています。
製品セキュリティ施策を推進するPSIRT活動は、2020年。月にCNA(CVE Numbering Authority)として認定され、製品の脆弱性情報を国際的に通用する形で管理・公開する能力と信頼性が認められています。サイバー攻撃対策としては、ネットワーク、端末、サーバー(クラウド)の一元管理と「多層防御」を導入し、サイバー攻撃の防御、不審な兆候や侵入の検知、即時対応を可能にし、被害の防止と最小化を図っています。
情報セキュリティマネジメントにおいては、PDCA(Plan・Do・Check・Act)サイクルによる継続的な改善活動を実施しており、これは変化の激しいサイバー脅威環境において、情報セキュリティ対策が陳腐化することなく、常に最適な状態を維持するための重要なフレームワークとして機能しています。具体的な目標として、米国国防総省が発行するサイバーセキュリティ成熟度モデル(CMMC)ver.2のレベル2以上を目指すといった、国際的な基準に準拠した目標設定も行っています。
JALグループは、万が一情報セキュリティ事故が発生した場合に備え、迅速かつ効果的な対応と再発防止を可能にする強固なCSIRT体制を構築しています。
インシデント発生時には、リスクマネジメントマニュアルに則り、情報セキュリティ専門組織を事務局とするJALグループCSIRT体制が発動され、被害の最小化と再発防止策の実施に重点を置いています。
実効性を確保するため、JALグループは年間2回以上のJALグループCSIRT訓練を計画・実施し、CSIRTメンバーの対応能力の維持・向上を図るとともに、組織全体の緊急時対応力を高めています。万一事故が発生した場合には、被害を最小限に留めることを最優先とし、速やかに必要な情報を公開し、再発防止策を含む適切な対策を講じる方針です。
サイバーセキュリティ強化のため、JALは外部組織との連携を通じて脅威情報の収集と共有を積極的に行っており、具体的には、交通・運輸分野の事業者の集団防御力向上に資する活動を推進する「交通ISAC」や、航空会社、航空機メーカー等で構成されるグローバルな情報共有組織である「Aviation-ISAC」に参画しています。これらの組織から得られた情報は、JALグループの情報セキュリティ対策の継続的な改善に活用されています。
複数の社外専門機関と連携し、24時間365日体制で不正アクセスやウイルス感染等の脅威を監視することで、異常を早期に検知し、迅速な初動対応を可能にしています。
公開サーバについては、ペネトレーションテストを含む脆弱性の網羅的な確認を実施し、外部からの攻撃経路となり得るシステムの弱点を事前に特定し、修正することで、実際の攻撃を受ける前にリスクを低減しています。
情報漏えい対策として、在宅環境での個人情報等の重要情報取り扱いに対し、社外で重要情報を取り扱うためのルールを詳細化し、社外で利用できる情報を明確にしています。
さらに、サイバーリスク対策として「ゼロトラスト」の考え方に基づいた新しいセキュリティ対策を導入し、社外で安全に利用できる会社端末の導入や、利用が拡大しているクラウドサービスの網羅的なリスク評価を推進しています。
全役員・社員を対象に情報セキュリティ研修を年間2回以上実施し、ウイルスメールやビジネスメール詐欺による被害を防止するため、標的型メール訓練を毎年複数回実施することで、社員の意識向上と行動変容を促しています。情報セキュリティ規程に違反した場合、懲戒を含む処分の対象とし、情報セキュリティを社員の評価の一部とすることで、規律を徹底しています。
専門組織による情報資産の管理状況の対面検査や情報セキュリティ規程への適合チェックをグループ会社も含め実施し、社外専門機関による年。回の監査を継続して実施することで、客観性と信頼性を確保し、継続的な改善を推進しています。
これらの事例に見られるように、CISOのリーダーシップの下で構築される明確な役割分担と多層的な組織体制、そして継続的な改善活動は、企業がサイバー脅威に直面した際に、被害を最小限に抑え、迅速に回復するための強固な「サイバーレジリエンス」を確立します。明確な役割分担を持つ専門組織の設置は、インシデント発生時に迅速かつ専門的な対応を可能にします。
例えば、CSIRTは被害の最小化と再発防止に特化し、PSIRTは製品の脆弱性対応を通じて顧客信頼を維持します。OTセキュリティグループは、ITとは異なる工場システムの特性に対応することで、生産停止などの物理的被害を防ぎます。これらの専門組織が連携し、多層防御やゼロトラストといった技術的対策と組み合わせることで、攻撃の各段階での防御力を高め、被害を局所化・最小化する効果が期待できます。
定期的な訓練(JALのCSIRT訓練、標的型メール訓練など)は、机上計画だけでなく、実際の運用における課題を特定し、改善サイクルを回すことで、組織全体の緊急時対応能力を実効的に高めます。PDCAサイクル、内外監査、外部連携は、変化の激しいサイバー脅威環境において、セキュリティ対策が陳腐化することなく、常に最適な状態を維持するための継続的な進化を促します。これは、情報セキュリティが単なる「防御」だけでなく、インシデント発生を前提とした「回復力」(サイバーレジリエンス)の構築に重点を置いていることを示しています。三菱電機がCMMCレベル2以上を目指す目標設定は、単なる国内法規遵守に留まらず、国際的なサプライチェーンにおける信頼性を高め、高度なセキュリティ要件が求められる領域での競争力強化を目指す戦略的な意図を強く示唆しています。このように、情報セキュリティは単なるコストではなく、事業継続性と競争優位性の源泉となることを明確に示しており、CISOの役割がインシデント発生時の迅速な対応と継続的な改善を可能にするという、本報告書の要件を具体的に満たしています。
4.CISOの役割進化:リスク管理を超えた企業価値の創造と保護
CISOの役割は、もはや単なるリスク管理や法令遵守に留まるものではありません。現代のCISOは、情報セキュリティを企業価値の創造、ブランド信頼の向上、そして競争優位性の確立といった経営機能へと進化させる役割を担っています。これは、セキュリティをコストではなく、戦略的な投資と捉える視点の表れです。
三菱電機グループは、情報セキュリティを「企業全体のレジリエンスと競争力を向上させるための戦略的な投資」であると位置づけています。情報セキュリティが事業戦略の策定、M&Aの検討、新規事業の開発といったあらゆる経営判断において考慮されるべき要素となり、結果として企業の持続的な成長に不可欠な競争優位性をもたらす可能性を秘めていると考えています。製品セキュリティ施策を推進するPSIRT活動がCNA認定を受けていることは、自社製品の脆弱性情報を国際的に通用する形で管理・公開する能力と信頼性が認められたことを意味します。この取り組みは、単なるリスク管理に留まらず、製品セキュリティを競争優位性の源泉と捉え、顧客に対する「安心」という付加価値を提供することで、ブランド価値の向上と市場におけるリーダーシップの確立を目指していると解釈できます。
情報セキュリティに関する研究開発にも積極的に投資しており、ペネトレーションテスト支援ツール「CATSploit」の開発や、AIにおける敵対的パッチによる攻撃への対策技術、ノウハウ保護が可能なセキュア実行技術(TEE)の開発も行っています。自社でセキュリティツールを開発したり、最先端技術の研究に取り組んでいたりすることは、三菱電機がセキュリティを「守り」だけでなく「攻め」の視点でも捉えていることを示します。
さらに、自社で培った情報セキュリティの知見と技術を社会に還元する取り組みも行っており、電子取引サービス「@Sign」や「ワンストップOTセキュリティソリューション」を提供することで、顧客企業のセキュリティ強化を支援しています。企業が自社のセキュリティ対策を外部にサービスとして提供することは、その内部的なセキュリティ体制が高度に成熟しており、市場のニーズに応えられるだけの専門性と実績があることの強い裏付けとなります。これは、情報セキュリティが単なるコストセンターではなく、新たな収益源となる可能性を秘めたビジネス機会であるという認識に基づいています。
JALグループは、情報セキュリティへの取り組みを「企業のレジリエンス(回復力)と持続可能性を確保するための戦略的な経営判断」として推進しています。今日のサイバー脅威が高度化・複雑化していることを認識し、予防対策を常に進化させ、十分な検知・監視体制を整えることで、「万全な対策を講じていく方針」を掲げています。これは、情報セキュリティ事故が不可避であるという前提に立ち、いかにその影響を最小限に抑え、迅速に回復するかという「サイバーレジリエンス」の概念に通じるものです。
JALは「交通ISAC」や「Aviation-ISAC」への参画を通じて脅威情報を収集・共有し、自社の情報セキュリティ対策の継続的な改善に活用していることは、個社単独での防御には限界があるという認識に基づき、「集団的防御」の概念を実践していることを示します。また、「ゼロトラスト」の考え方に基づいた新しいセキュリティ対策を導入し、社外で安全に利用できる会社端末の導入やクラウドサービスのリスク評価を推進しています。
これは、従来の「境界防御」モデルから脱却し、「何も信頼しない」という前提で全てのアクセスを検証する、より強固なセキュリティモデルへの移行を意味し、JALの先進的なセキュリティ戦略を示しています。情報セキュリティ規程違反に対する懲戒処分や社員評価への反映は、情報セキュリティが個人の責任として明確に位置づけられ、組織全体として情報セキュリティの重要性を徹底し、リスクを低減するためのガバナンスとコンプライアンスの側面からのアプローチです。
これらの事例から、セキュリティが「コストセンター」から「プロフィットセンター/競争優位性」へと転換していることが明確に見て取れます。三菱電機の事例では、高度なセキュリティ体制と専門知識(OTセキュリティ、PSIRT、研究開発)が内部的な成熟度を高め、その結果として外部へのソリューション提供という新たなビジネスモデルが生まれています。これは、セキュリティ投資が直接的な収益源となり得ることを示唆しており、CISOが単なるリスク管理責任者ではなく、事業開発やイノベーションにも貢献する経営者としての役割を担っていることを意味します。製品セキュリティの強化とCNA認定は、顧客への「安心」という付加価値を提供し、ブランド信頼と市場での差別化に繋がります。
JALが重視する「サイバーレジリエンス」は、インシデント発生時の迅速な回復能力だけでなく、顧客や社会からの信頼維持に直結します。航空事業のような公共性の高い分野では、セキュリティ事故は運航の安全性やブランドイメージに壊滅的な影響を与えかねません。したがって、強固なサイバーレジリエンスは、事業継続性を保証するだけでなく、顧客がJALを選択する際の決定要因となり、結果として競争優位性を確立する重要な要素となります。両社の取り組みは、情報セキュリティが「セキュリティ・バイ・デザイン」の思想に基づき、製品やサービスの企画・開発段階から組み込まれることで、その品質と信頼性を高め、それが企業価値の創造に繋がるという、より広範な経営戦略の一部となっていることを示しています。CISOの役割は、リスクを「管理する」という守りの機能から、セキュリティを「事業機会」と捉え、「企業価値を創造し、保護する」という攻めの経営機能へと明確に進化しているのです。これは、現代の企業が直面するデジタルリスクを乗り越え、未来を切り拓くための不可欠な投資であり、経営戦略そのものであるという、本報告書の主張を具体的なビジネス成果と結びつけて強力に裏付けています。
5.結論
ここでは、三菱電機グループとJALグループの先進的な取り組み事例を詳細に分析し、CISOの役割が単なる「肩書き」から「責任構造の中核」へと昇華し、さらに「企業価値を創造し、保護する重要な経営機能」へと進化していることを述べました。
両社は、情報セキュリティを経営の最重要課題と位置づけ、CISOを経営層に直結させることで、トップダウンでの強力な推進体制を確立しています。これにより、情報セキュリティは単なるIT部門の責任に留まらず、全社的なリスク管理、事業継続性、そして競争優位性の源泉として、経営戦略に深く組み込まれています。
明確な役割分担を持つCSIRT、PSIRT、OTセキュリティグループといった専門組織の設置、多層防御やゼロトラストといった先進的な技術的対策、そしてPDCAサイクルに基づく継続的な改善活動、定期的な訓練、内外監査、外部連携といった取り組みは、インシデント発生時の迅速な対応と被害の最小化を可能にし、企業のサイバーレジリエンスを飛躍的に向上させています。
さらに、CISOの役割は、リスク管理を超えて、製品・サービスのセキュリティ品質向上を通じたブランド価値の創造、自社のセキュリティノウハウを外部にソリューションとして提供することによる新たな収益機会の創出、そしてサイバーレジリエンスの確立による持続可能な成長基盤の構築に貢献しています。これは、情報セキュリティ投資が単なるコストではなく、企業が未来を切り拓くための不可欠な戦略的投資であることを明確に示しています。
現代の複雑なデジタルリスクを乗り越え、持続的な成長を実現するためには、CISOの役割を最大限に活用し、情報セキュリティを経営の根幹として位置づけることが不可欠です。企業がCISOのリーダーシップの下でセキュリティを経営戦略の中核に据えることで、顧客や社会からの信頼を維持し、デジタル時代における競争優位性を確立していくものと確信します。